味噌作り特集
お味噌の作り方

手作り味噌の作り方
美味しい味噌を作るポイントは?

- 酵素力の強い元気なこうじを使用する
- 大豆を柔らかく煮る
- 食塩を均一によく混合する
美味しい味噌作りは、元気で強い米麹選びから!
当店のこうじは、酵素力の豊かな、生こうじです!

お味噌の材料
- 大豆 1kg
- 米こうじ 1kg
- 食塩 500g
基本の配合割合は、米こうじ:食塩=1:1:0.5
甘くする場合は、米こうじを増して、減塩にします。
塩の量は変えません。
米こうじ 1kg→1.2kg~1.5kg
※食塩の量を変えないのがポイントです。特に減塩味噌の場合は、食塩の量を減らさずに米こうじの量を増やしてください。
ご用意いただくもの
- 大きめの鍋 (大豆容積の2.5倍以上)
- ボウル
- ザル
- 大豆をつぶす道具
(すり鉢、マッシャー、すりこぎ、フードプロセッサーなど) - 容器 (ポリ樽もしくは桶など)
- 内ふた
- 重石
- ビニールラップ (味噌の表面に当てるため)
- 種水 (一度沸騰させて冷やした水)
※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返してのせてもOK。
いよいよ仕込みをスタートしましょう!
大豆を水でよく洗います。
大きめの容器に水をたっぷり入れ、洗った大豆を一晩(約8時間)浸しておきます。
(一晩経つと、大豆の容積が約2.5倍になります)

大きめの鍋に大豆とたっぷりの水を入れ煮立て、沸騰したらコトコトと弱火で、柔らかくなるまで煮ます。柔らかくなるまで、2時間以上かかります。
めやすは、親指と人差指を使って、縦につまんで押しつぶれるくらいまで煮てください。二つに割れるのは、まだ煮方が不足しています。
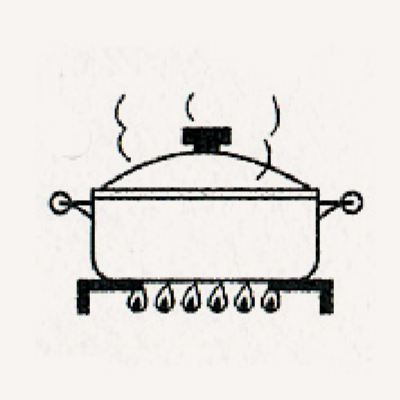
煮えた大豆をザルにあげ、40℃くらいまで冷まします。

すり鉢、ミートチョッパー、マッシャーなどを使用し、すりつぶします。
(大豆をビニール袋に入れて、タオルを敷き、空き瓶などでたたきつぶす方法もあります)

こうじをよくバラして塩を加え均一によく混合します。
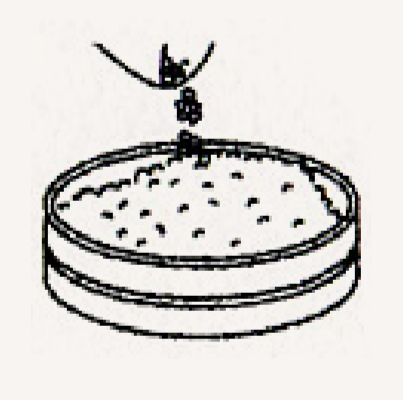
すりつぶした大豆と、(5)の塩切こうじをよく混合します。
(この時、”種水”を入れてもよい)
※種水は一度沸騰させて冷やした水を使用してください。
※種水の量は大豆1kgの場合、100cc~150ccを一応の目安。
※大豆は柔らかく煮て、固めに仕込むのが、みそ作りのコツ!

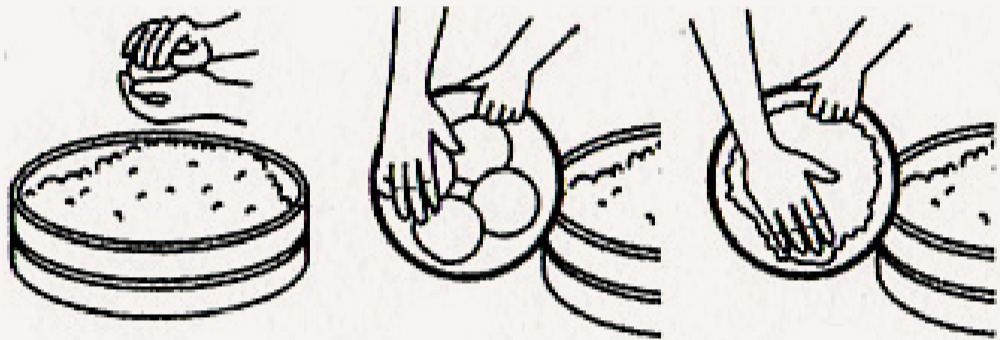
詰め終わったら、表面に厚手のビニールをあて、空気が直接ふれないようにする。

内ふたをのせ、その上に約500g~1kgの重石をのせます。
※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返して、のせてもOK。
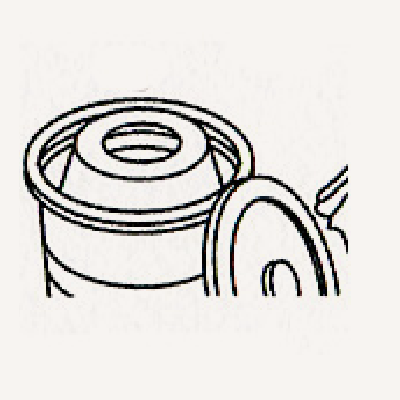
外ふたをして、容器の中にゴミなどが入らないように、新聞紙かビニールでおおい、ひもで縛ります。仕込んだ容器は、風通しのよい冷暗所で保存してください。
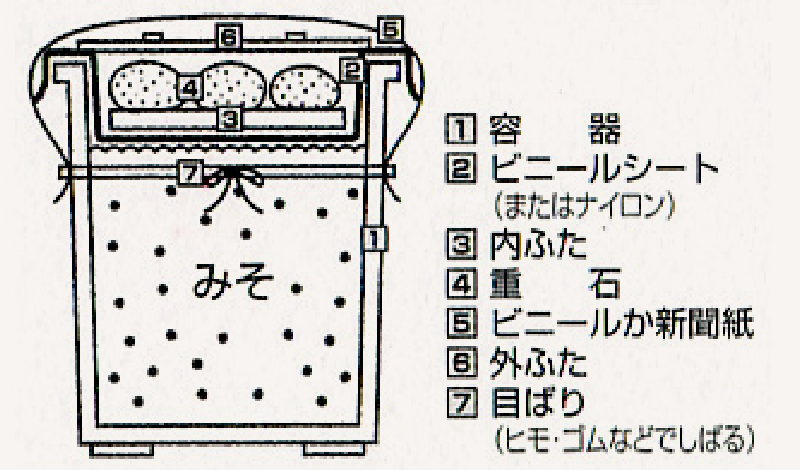
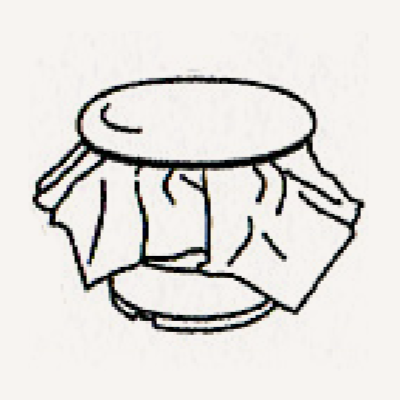
※画像の無断転用はご遠慮願います。
熟成期間と食べごろの目安
仕込みの季節より、熟成期間が異なります。
めやすとして10月~4月頃の仕込みは、6~8ヶ月間、その他の月に仕込んだ場合は、4ヶ月間熟成期間が必要です。
みそは生きています。熟成期間の違いは、味・香りの違いになります。”我が家のみそ味”を作るのは、熟成期間です。食べ頃は忘れないようにカレンダーなどに印をつけておくとよいでしょう。
長期熟成みそをお好みの方は、夏と冬の気温変化が少ない冷暗所に保管してください。

出来上がり
- 食べ頃になったら、重石・内ふたをとり、ビニールに残っている「みそカビ」を取り除いてください。
- みそを上下によく混ぜます。これで出来上がり。
- 必要な分を別の容器に小分けしてお召し上がりください。残りのみそは表面を平らにして、ラップやビニールシートを密着させ、空気にふれないようして冷蔵庫、または冷暗所に保存してください。(こうじが再び活動し、みその色が変化したり、「みそカビ」防止のため)
みそカビ対策豆知識
みそが発酵すると、表面に白色や赤茶色や黒色に変色した味噌が出来ます。これを「みそカビ」と言います。
「え!?味噌づくり失敗!?」
いえいえ!特に害はありませんのでご安心を。でも、お味噌の風味が損なわれますので、取り除いてくださいね。
みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。
みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。
洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。
味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。

こんな作り方もあります!
少量での味噌作りの場合、なんと、
ジップロックバッグを使用して作ることができます!
以下の点にご注意下さい。
空気をしっかり抜くこと。空気が残っていると(特に四隅)カビが発生しやすくなります。また容器に比べて、非常に薄く透明のため、温度に左右されやすく紫外線もそのまま通すので、必ず暗い、涼しいところ(←冷蔵庫は× ダメ)で保存してください。
さらに、時々(2ヶ月に一度ほど)揉むと良いです。(ジップロックのコンテナは、ポリ樽やタッパーでの仕込みと同様にお考え下さい)








